- 急速進化するAI技術と企業の未来を切り拓く最新動向
- 1. AIニュース最新動向と社内データ活用の革新
- 2. AIツールの多様化と実用性強化
- 3. 生成AIビジネス活用事例と社会的課題
- 3.1 SalesforceのAgent Forceによる営業自動化
- 3.2 金融業界におけるAIエージェント導入事例
- 3.3 博報堂「細田AI」事例に学ぶ組織内知識のAI化
- 3.4 ExaWizardsのバディーエージェントとRPA自動化
- 3.5 マーケットエンタープライズに見る組織全体のAI活用推進
- 3.6 フィジカルAIとロボティクスの最新動向
- 3.7 AIデータ保存問題とプライバシーリスク
- 3.8 AIによる職場の変革と失業問題の社会的影響
- 3.9 生成AI利用による生産性向上と職場評価の課題
- 3.10 生成AI自社開発の投資効果と多ツール導入の重要性
- 3.11 生成AIを用いた消費者の商品・サービス検討行動の変化
- 3.12 教育現場のAI利用状況と世代間ギャップの課題
- 4. まとめ:AI時代の最新トレンドと未来への展望
急速進化するAI技術と企業の未来を切り拓く最新動向
近年、AI技術の劇的な進化により働き方や情報活用のスタイルが大きく変わっています。特に生成AIやAIエージェントの分野では、技術革新が日々進み、多くの企業が業務効率化や新規事業開発に積極的に取り組んでいます。中でも、社内データを自在に分析・活用できるChatGPTのディープリサーチ機能や、Googleの最新AIモデルGemini 2.5 Proの性能向上は、実務での実用性を大きく高めています。これらの技術は企業の知的資産を活かし、働き方改革や製品開発、顧客対応など多様なシーンで新たな価値創造を支援しています。
AIの進展は技術的側面にとどまらず、営業自動化やクリエイティブ制作支援、ロボティクスを活用したフィジカルAIへと応用が拡大し、企業活動の変革を促しています。最新のAIツールは単一機能ではなく、共有ノート、コード自動レビュー、多モデル比較など多機能プラットフォームとして進化し、多様なユーザーニーズに応えています。
一方で、生成AIの普及に伴い、労働市場や社会にも変化が生じています。Anthropic社CEOが指摘するように、エントリーレベルのホワイトカラー職の代替やスキルアップの必要性、プライバシー問題など、社会的な影響が拡大していることも見逃せません。こうした課題は経営戦略や人材育成の重要テーマであり、迅速かつ継続的な情報把握と対応が求められます。
私が日々接する最新AI技術は、性能向上によりビジネスからクリエイティブ制作まで幅広い用途での活用が進んでいます。例えば社内の膨大なドキュメントを瞬時に検索し、議事録の自動生成や要件定義書の作成支援など、業務効率を飛躍的に高める機能が実用化されています。こうしたツールの正しい理解と活用が生産性向上の鍵となります。
以下では、注目のAIニュースや最新ツールの機能、活用事例、さらに生成AIがもたらす社会的課題まで幅広く解説します。特にChatGPTの社内連携機能やGoogle Geminiモデルのアップデートは企業のAI利活用を次の段階へ押し上げる重要ポイントです。加えて、NotebookLMの共有機能や営業自動化の実例、ロボティクスとAI融合の最新動向など、多角的に最新トレンドを紹介します。
ChatGPTの進化により社内データを活用したディープリサーチが可能になりました。これにより経営判断や企画立案の効率化が飛躍的に進んでいます。
GoogleのGemini 2.5 Pro最新版はウェブページプレビューやAPI連携による自動生成機能が強化され、クリエイティブの質と速度が大幅に向上しています。こうしたツールの普及で専門知識の有無に関わらず多くのユーザーがAIの恩恵を受けられる環境が整いつつあります。
AIツール導入にあたっては、社内の運用体制整備やセキュリティ対策も不可欠です。例えば全社での活用推進チームの設置や具体的な事例共有による教育などが必要です。こうした点は弊社のAIスミスでも詳しく紹介しています。
また、AI活用は業務効率化だけでなく営業支援や顧客体験の高度化にも直結しています。SalesforceのAgent Forceや博報堂の「細田AI」など先進的事例は業界や企業規模に応じたAI活用の参考例となっています。
生成AI技術の進化がもたらす社会課題としては、労働市場の変化、プライバシー問題、職場でのAI利用評価に関わるバイアスなど多角的な議論が進んでいます。これらはAI導入企業にとって避けて通れないテーマであり、長期的な対策が求められます。
私は最新AI技術の発展と共に「情報を戦略的に活用し未来に備えること」が今最も重要だと実感しています。最新技術トレンドを知ることでこれからのビジネスに必要なスキルや思考法を効率的に身につけることができます。
仕事や生活にAIを取り入れるヒントとして、先端技術の動きを敏感にキャッチし、その恩恵を最大限活かすことで時代の変化に確実に対応できます。まずは最前線の情報収集を通じてAI活用の実践的知識を深めましょう。
興味深いAIソリューションや業界別活用事例は、弊社のAI開発会社比較記事や法人向けAIツール比較記事もぜひご覧ください。ビジネスとAIの交差点で新たな未来を切り拓くヒントが見つかります。

1. AIニュース最新動向と社内データ活用の革新
AI技術の進化は止まることなく、新機能やモデルのアップデートが日々発表されています。特に社内データの活用を可能にした生成AIの進展は、ビジネス効率化に大きなチャンスをもたらしています。ここでは、ChatGPTのディープリサーチ機能からGoogle Gemini 2.5 Proの性能向上まで、最新の実践的技術動向を詳しく紹介します。
1.1 ChatGPTの社内データ対応とディープリサーチ機能
OpenAIのChatGPTに実装された新しいコネクター機能は、GitHub、Gmail、Googleドライブ、カレンダー、Outlookなど多様なクラウドサービスと連携し、社内の膨大なデータにアクセスして深い情報探索を実現しています。さらにBoxやDropbox、HubSpotなどのクラウドストレージも追加可能で、MCP(Model Context Protocol)を活用し既存連携以外のツールも柔軟に接続できます。
例えば、過去3ヶ月以内に作成したAIエージェント関連の社内資料を抽出し、内容とファイル名をリスト化するよう依頼すると、ChatGPTはGoogleドライブを検索して関連資料を効率的にピックアップします。最新AIトレンドやマーケティングへの生成AIの影響など、テーマに沿った過去データの集約と根拠に基づく内容作成を支援します。
このディープリサーチ機能は、スタッフの入れ替えによるナレッジ断絶が起こりやすい企業環境で特に効果的です。元々はウェブ情報の検索が中心でしたが、社内データ連携の開始により利用価値が飛躍的に向上しています。期間やフォルダを細かく区切って調査を繰り返し、AIの回答の精度を見極める運用が推奨されます。
社内データ連携に関する詳細はChatGPT Deep Research社内データ対応をご覧ください。
1.2 ChatGPTレコード:音声録音から議事録までの新機能
Macデスクトップ版ChatGPT限定で提供されている「ChatGPTレコード」は、会議音声をリアルタイム録音し、終了後に自動で議事録を作成できる新機能です。手動のメモ作成負担を大幅に軽減し、ワークフロー効率化に貢献しています。
私自身の体験感覚では、Notionの録音機能と比べるとチャット履歴へのデータ蓄積は薄い印象ですが、Mac利用者にとっては気軽に会議録音やアイデア収集に活用できる点で有用です。音声起こしと議事録作成が一体化し、リモートワークや分散チームの情報共有ツールとして期待が高まっています。今後の他OS対応も注目される機能です。弊社でも現在、音声データから議事録が自動で作れるツールの開発にも取り組んでいるところでもあります。
1.3 Gemini 2.5 Proの性能進化と新機能紹介
GoogleのAIモデルGeminiは2024年5月に2.5 Proバージョンがリリースされ、知能指数や性能が大幅に向上しました。最新のバージョンでは各種評価指標の向上が確認され、実務利用価値が増しています。
弊社のスタッフも業務で利用し、高い回答品質を実感しています。データ量や問いかけ方の工夫により、より正確で実用的な結果を得られる場面が増加。IQテスト評価では他モデルと肩を並べる水準に達しています。
GeminiはHTMLコード生成のリアルタイムウェブプレビュー機能を強化し、「Gemini機能追加ボタン」によりAPI連携でキャッチコピー生成やPythonコード作成など多彩な自動処理がウェブ上で可能になりました。広告制作や新規AIエージェントの発想支援など、多様な業務支援がワンストップで実現します。カレンダー連携やルーティンタスク自動化も開発中で今後の実装が期待されます。
詳細はGemini 2.5 Pro最新バージョンでご確認ください。

2. AIツールの多様化と実用性強化
多種多様なAIツールが登場し、それぞれが独自の機能でユーザーのニーズに応えています。ここではGeminiのプレビュー連携、NotebookLMの共有機能、SquarespaceのAIサイト制作、Perplexityの社内検索強化、Mapifyのマインドマップ機能、ManusのAIスライド作成機能を紹介します。これらは生産性向上に直結し、スマートな業務遂行を支援します。
2.1 GeminiのウェブページプレビューとAPI連携機能
Geminiは生成したHTMLコードを即座にウェブページとしてプレビュー可能です。単なるコード出力を超え、完成形のページイメージをリアルタイムで閲覧できます。新たなAPI連携機能により、ウェブページ内にGeminiボタンを設置し、押すだけでキャッチコピー自動生成やPythonコード作成などが実行可能です。
これによりアイデア出しやコンテンツ作成の効率が飛躍的に向上。AI研修向けコンテンツではユーザーが直接生成AIに質問したり、新規エージェントを想定するなど双方向インタラクションが可能です。動的に進化する未来型Web体験の先駆けと言えます。
Geminiの拡張機能は業務効率化やクリエイティブ制作現場での活用価値が高まっています。
2.2 NotebookLMの共有機能解説と活用シーン
GoogleのNotebookLMは個人の知識ベースをAIチャットと組み合わせて活用できる革新的ツールです。待望の共有機能により、作成したNotebookをリンクで簡単に共有可能となりました。
共有設定では「チャットのみ」表示と「Notebook全体」表示を切り替え可能で、閲覧者のアクセス範囲を柔軟にコントロールできます。編集権限を付与すれば共有相手が情報更新や生成も可能です。
この機能は社内外のナレッジシェアに役立ち、営業資料、製品マニュアル、研究レポートの共有やフィードバックに活用されています。ラグチャット的対話AIの簡単展開も可能で、企業の情報資産活用を大幅に進化させます。
現状は個人プラン中心でワークスペース制限がありますが、今後の拡充が期待されます。詳しくはNotebookLM共有機能をご参照ください。
2.3 SquarespaceによるAI活用のウェブサイト制作
SquarespaceはAIを活用し、誰でもプロ品質のウェブサイトを作成できるサービスです。世界200カ国以上で利用され、日本でもサービス開始。ドメイン取得、サーバー管理、SEO対策までワンストップ対応可能です。
AIによるデザイン提案が特に好評で、サイト名やブランドイメージを入力すると最適なコンテンツ配置やカラーデザインを自動で提案。コンサルティング、ECサイト、ブログ、イベントページなど多様な用途に対応し、初心者でも充実したオンラインプレゼンス構築が可能です。
筆者の利用体験では問い合わせフォームやオンラインコース導線の整備が速やかで、サイト制作時間短縮と質向上に貢献。14日間無料トライアルと初回10%割引クーポンもあり、導入ハードルが低いのも魅力です。
AI自動生成と直感操作の組み合わせが今後のウェブ制作のスタンダードになるでしょう。
2.4 Perplexityの社内データ検索対応強化
検索特化型AIツールPerplexityはGoogle Workspaceとの連携が強化され、Gmailやカレンダー情報を検索対象に追加。個人のスケジュールやメール内容を踏まえた具体的回答が可能になりました。
PerplexityはGoogleドライブやOneDriveとも連携し、ユーザーがチャット画面で対象ファイルを指定して検索します。今回の機能強化によりスケジュール管理とメール内容の検索が直結し、業務効率化に貢献します。
また、社内検索においてChatGPTなど他AIツールとの相互活用も進んでいます。BoxやDropboxのディープリサーチ機能と連携することで社内データ活用の幅が拡大しています。
社内情報活用を目指すならPerplexityの新機能は注目です。詳細はPerplexity AIで確認可能です。
2.5 Mapify最新アップデートとマインドマップ活用術
Mapifyはマインドマップ作成ツールとして継続的に進化しています。最新アップデートでユーザーインターフェースが刷新され、左側画面の整理と操作がスムーズになりました。
特にタグ付け機能が追加され、膨大なノードに複数のタグを付与し、検索や絞り込みが容易に。例えば「ChatGPT追加」タグで関連トピックのみ表示でき、情報管理効率が向上します。
私はMapifyを個人の情報ブックマークに活用し、タグ機能導入で目的資料へのアクセス速度が格段に向上。専門領域やリサーチ、プロジェクト管理に有用で、情報肥大による混乱防止に役立ちます。
詳しくはMapify をご覧ください。
2.6 ManusのAIスライド生成機能とプレゼン効率化
ManusはAIスライド作成ツールとして注目され、新機能「AIスライド」を追加しました。従来のGenspark似のシンプル操作に加え、グラフィカルでビジュアル表現を重視したプレゼン資料作成に強みがあります。
公式動画によると、テキスト入力だけで魅力的なスライドが生成され、背景画像やカラーデザインも自動提案。PDF書き出し対応や編集機能も充実し、PowerPointに不慣れなユーザーもスムーズに資料作成可能です。
編集柔軟性と仕上がりの美しさはビジネスプレゼンや教育教材作成の生産性向上に寄与。AIアシストによる資料制作が増加する中で、効率的なプレゼン作成を求める方に推奨されるツールです。
詳細はManusをご覧ください。

3. 生成AIビジネス活用事例と社会的課題
生成AIの急速な普及は、営業自動化や金融サービス、組織内知識共有など多様な分野でのビジネス変革を促しています。ここでは主要な活用事例と、フィジカルAI、プライバシーリスク、労働市場の変化など社会的課題について掘り下げます。
3.1 SalesforceのAgent Forceによる営業自動化
Salesforceの「Agent Force」は営業部門向けAIエージェントで、メール、SMS、チャットを自動化し、見込み客発掘からフォローアップまで効率化します。M&Aセンターなどで導入され、顧客情報を活用した新商機の発掘に活用中です。
1トランザクションあたり約10円のコストが発生しますが、営業効率とリードナーチャリングの質向上に寄与。今後は営業担当者へのフィードバック機能も強化され、ジュニア営業マンの提案力向上が期待されています。
3.2 金融業界におけるAIエージェント導入事例
金融業界ではBNY Mellonが「イライザ」AIツール群を展開し、13種類の専門エージェントが連携して顧客対応や商品提案を最適化。顧客情報や銀行商品データを部門別に管理し高精度サービスを実現しています。
ゴールドマンサックスは社員業務フローをAIに模倣させ、パーソナライズされた金融アシスタントを提供。個別の考え方や業務スタイルに即した支援を行っています。
特に注目されるのはキャピタルワンの自動車ローンのAIエージェント。ディーラー向けに車購入プロセス全体を支援し、高機能サービスを簡便に提供。これは不動産や旅行、結婚相談所など仲介プラットフォームへの応用が期待されるモデルです。
3.3 博報堂「細田AI」事例に学ぶ組織内知識のAI化
更に国内では博報堂の「細田AI」は優秀社員の思考パターンやノウハウをAI化し組織に展開しています。コピーライティングや分析業務で成果を挙げ、営業担当者がクリエイター相談前に質問し効率化を実現しています。
この事例は、企業独自の知識をAIに取り込むことで差別化要素を生み出す戦略の好例。共通の基幹AIモデルを活用しつつ、独自ファインチューニングで競争力を強化しています。
3.4 ExaWizardsのバディーエージェントとRPA自動化
ExaWizardsは高度AIとRPAを組み合わせた「バディーエージェント」を展開。複数専門エージェントが協働し、業務自動化・効率化を支援。RPA設定をAIが補助し、一度の操作で繰り返し業務を自動化します。
既に2000社以上で導入され、医療、金融、製造業など幅広く活用。AIエージェント群による効果的業務改革事例として注目されています。
詳細はExaWizards バディーエージェントをご確認ください。
3.5 マーケットエンタープライズに見る組織全体のAI活用推進
マーケットエンタープライズは社員の約95%が生成AIを日常業務で活用し、月間6,268時間の効率化を達成。社内でプロンプト事例共有や動画活用推進が進み、有償Google Geminiも全社導入済みです。
社内データ活用の検索システム(RAG)や営業ロールプレイ研修も推進し、生成AI活用文化を組織全体で育成。中規模・ベンチャー企業のAI競争力強化モデルとして示唆に富みます。
マーケットエンタープライズ社へご興味のある方はリンクを貼っておくので、ご参照ください。
3.6 フィジカルAIとロボティクスの最新動向
生成AIの話題が多い一方、フィジカルAI(ロボット技術)も着実に成長。2024~2025年に調達額増加が顕著で、Figure、アプトトロニック、スキルドAIなど主要企業が活発に活動しています。産業用から家庭用ロボットへの応用も視野に。
Figureは年内中までに数千台の家庭用ロボット投入予定。Amazonはヒューマノイド配送ロボットの実証実験を開始し、自然言語指示に対応し配送業務の完全自動化を目指しています。倉庫内ロボット連携から自動運転配送まで全自動化は数年以内に実現の可能性大。
こうした動きは労働市場や人材育成に大きな影響を及ぼすため、最新情報の継続的把握が重要です。特に近年、中国市場でのAI+ロボティクスの発展が目覚ましいことからも、こうした技術に注目しておくことで、シンギュラリティが目の前にあることも実感できるでしょう。
家庭用ロボット開発を続けるFigure AI・Agility Roboticsのリンクも貼りましたので、ご参照ください。
3.7 AIデータ保存問題とプライバシーリスク
OpenAIのチャットデータ無期限保存問題が顕在化し、契約内容やプライバシー保護の観点から批判や訴訟が相次いでいます。API利用者のデータは従来30日で削除が通例でしたが、実際には削除されていないケースも。
この問題はセンシティブ情報の取り扱いにリスクをもたらし、企業のAI導入には契約内容確認や厳格なデータ管理体制が不可欠。今後、法規制や運用基準の整備が求められますが、現実には、まだまだ法が追いついていない状況にあります。AIに相談や対応をお願いする場合、情報は常に採られているものとして使って行くと言う割り切りも大切なのかもしれませんね。
3.8 AIによる職場の変革と失業問題の社会的影響
Anthropic社CEOダリオ・アモデー氏は、今後1~5年でエントリーレベルのホワイトカラー職の最大50%がAIに代替され、失業率が10~20%に達する可能性を警告。特に技術、金融、法務、コンサル分野で若年層への影響が大と述べています。
高失業率は社会不安定を招き、政治的混乱も過去に多数発生。政府・企業はAIの進展を正しく認識し、迅速かつ透明な議論と対策が不可欠。
対策案としてAI利用機会の再分配トークン制度やAI利用課税の社会保障充当などが提案されており、制度設計は経済の持続的発展に極めて重要です。
詳細はGigazineの記事(AIでホワイトカラーの初級職の半分がなくなり今後5年以内に失業率が20%まで跳ね上がる可能性があるとAnthropicのCEOが見解を公表)をご確認ください。
3.9 生成AI利用による生産性向上と職場評価の課題
この調査では生成AI活用で生産性が平均3倍向上。従来90分の作業が30分に短縮されることも。執筆、批判的思考、学習戦略などで特に効果が顕著であると言うことでした。
一方、職場でAIツール使用者が「怠惰」「能力不足」と評価されるバイアスも報告。上司・同僚の偏見により、AI使用を隠す傾向があるため生産性向上の足かせになっていることも報告されています。
この課題解消には職場文化の変革とAI理解促進が不可欠で、AI活用を正当評価する環境整備が急務です。
詳細はPNAS AI職場評価研究をご参照ください。
3.10 生成AI自社開発の投資効果と多ツール導入の重要性
多くの企業が生成AIツールの自社開発に約3,000万円を投資し、17%が300%以上のROIを達成。しかし機能追加やアップデートは困難で、SaaS型ベースツール活用が効率的との意見もあります。
ROIが高い企業は複数AIツールを組み合わせ運用し、社内問い合わせ対応や企画開発で顕著な効果をあげています。単一ツール依存を避け最適ツール群を活用することが成功の鍵です。
以前書いた記事になりますが、法人向けAIツール比較記事があります。ここでは、様々な法人向けAIをご紹介しているので、ぜひご覧ください。
3.11 生成AIを用いた消費者の商品・サービス検討行動の変化
この調査によるとAIツールを使った商品・サービス検索経験者は約6割。そのうち約7割が生成AIで商品検討を完了。
価格帯や推奨条件指定でAIがレビューや口コミを瞬時に提供することから、その利便性に利用者も続々と増加中とのこと。企業は情報の最適化や生成AI活用マーケ戦略の検討を強化すべき時期に来ていると言えるでしょう。
EC運営者や商品企画担当者は生成AI活用を無視できる時代では無くなってきています。これまで力をいれていたSEO対策だけでは、商品が売れる時代では無くなってきているのです。SEOと生成AIの両輪で戦略策定が必須になってきています。
私が先日、書いた生成AI×SEO活用記事も是非、ご一読してみてください。現状はAIだけに頼らず、SEOにもよらないハイブリット型のSEO対策が重要であることがよく分かると思います。
3.12 教育現場のAI利用状況と世代間ギャップの課題
小中学生の約4~5割が作文構成や数学解説にAI活用。AlexaやSiriも高利用していると言います。
一方、家庭・学校でAI利用ルールを明確にしているのは約1割に留まっているそうです。利用法のばらつきと世代間ギャップが拡大していることが、よく分かります。
親や教師はAIを安全かつ効果的に子どもに使わせるため、利用ガイドラインと教育カリキュラム整備を急ぐ必要がありそうですね。もちろん自由にAIに触れさせることも大事ですが、一方でルールやモラルが必要な時代にAIは入ってきたのかもしれません。
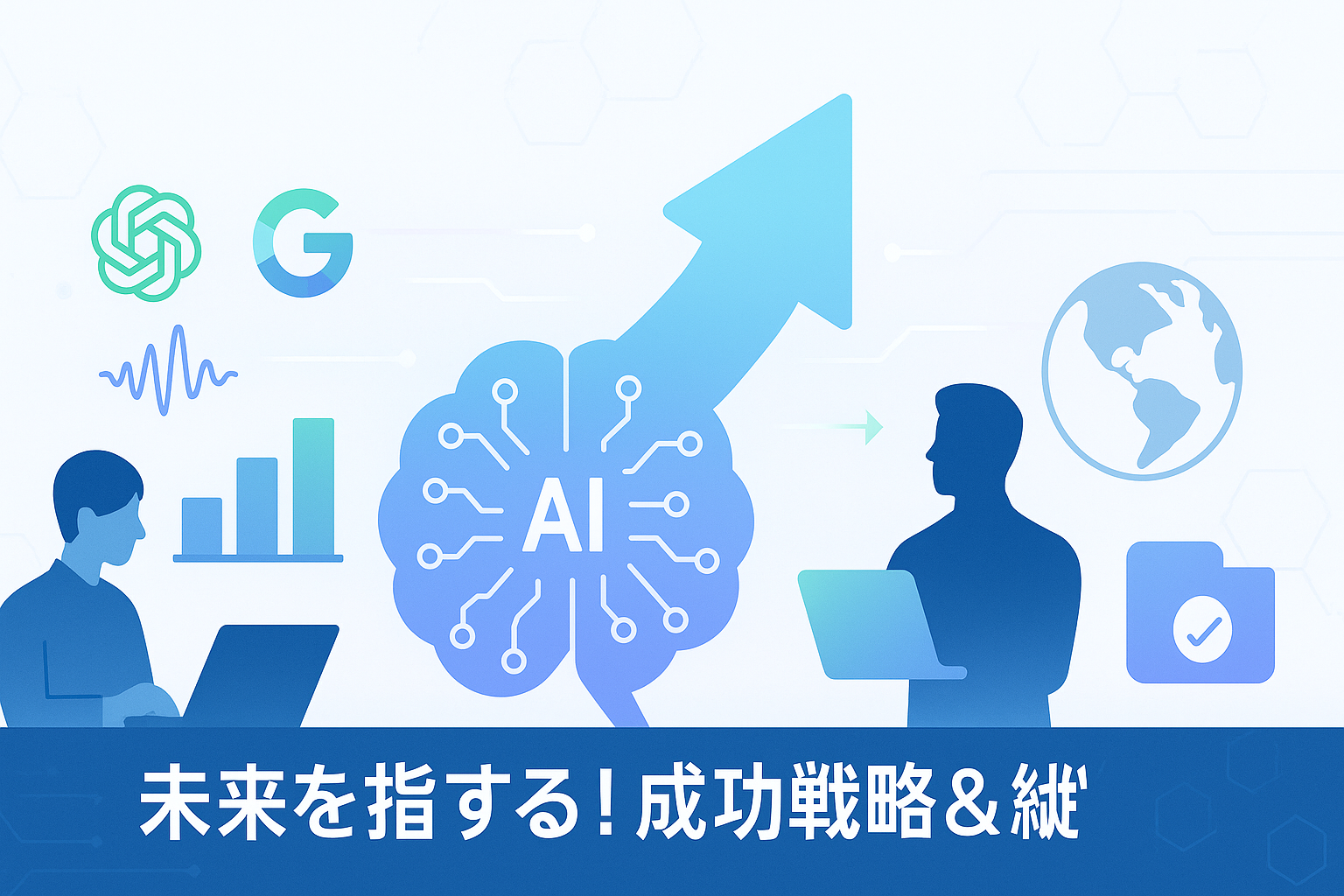
4. まとめ:AI時代の最新トレンドと未来への展望
AIの急激な進化は働き方やビジネスプロセス、社会構造を根本から変革しています。取り上げた最新AIニュースや事例を踏まえ、注目すべきポイントと今後の取り組み方を整理します。
4.1 社内データ活用の新フェーズ
ChatGPTなど大規模言語モデルが社内データに直接アクセスしディープリサーチが一般的になってきました。これにより企業情報資産の活用価値が飛躍的に向上し、GoogleドライブやOutlook資料の効率検索で資料質向上や業務効率化が進んでいます。
活用時は対象データ範囲や期間の適切設定、AI性能の見極めが重要で、情報資産管理とAI技術融合がDX推進の鍵となりそうです。
4.2 多様化するAIツールの使いやすさと創造性向上
Gemini 2.5 Proの性能強化、NotebookLMの共有機能、SquarespaceのノーコードAIサイト制作など、多彩なツールが柔軟なAI活用を後押し。GeminiのAPI連携により双方向Webサービスが実現し、ノート共有やマインドマップ機能がコラボレーションを促進。
こうした進化は生産性と創造性の底上げに直結し、積極的な習熟・導入が業務革新の近道です。
4.3 技術革新がクリエイティブと開発支援を変革
音源分離、AIアバター動画、感情表現コントロール音声生成などクリエイティブ領域の進展が顕著になってきています。SunoやHeyGenは専門知識不要で高度コンテンツ制作を実現が出来ています。(FaceBookなどの詐欺広告もこれらの技術が使われていることは明らかです)
Cursor 1.0のコード自動レビューやバグ検出機能は開発現場でAIの不可欠性を示し、ホワイトカラー業務全般に波及することは時間の問題で、仕事の質と効率を根本改善する可能性を秘めています。
4.4 実務適用と社会課題の拡大
Salesforce Agent Forceの営業自動化や金融の複数AIエージェント連携、博報堂細田AIの知見AI化など実務適用事例が増加していると言うお話もしました。こうしたAIの取組は、企業競争力が活性化する元となっています。
一方、OpenAIのログ無期限保存問題や失業リスクなどプライバシー・労働市場課題も少しずつ浮き彫りになってきています。リスキリングや所得再分配制度などAI時代を迎える私達には、社会整備が急務とも言えそうです。
技術恩恵が得られるのは有り難い話ですし、もちろんそこで得られる実務の効率化は、これからの社会発展においてはなくてはならないものでしょう。その一方で倫理的・制度的対応の両立が不可欠になっているのも、また事実です。これから、こうした課題とも向き合っていかなければ、なりませんね。
4.5 生産性向上と職場評価の新パラダイム
生成AIで業務生産性平均3倍向上であったり、時間圧縮による創造的な業務へシフトしていくことがよそうされていますね。。
しかしAI使用者に対する「怠惰」評価などは、まだまだ現実社会ではAIが受け入れられていない現実もあります。会社はAIに対しての理解促進と評価基準をしっかり作っていかなければ、そうした法人はどんどん失われていくことも想像に難くありません。いかがですか?みなさんのまわりでも、そうしたことが現実に起きているのでは無いでしょうか?
4.6 多ツール戦略と消費者行動変化
生成AIツール複数導入で3000万円投資、ROI300%超も多数。そんな話をよく聞きます。そうした企業の多くは、単一ツール依存ではなく最適ツール群の組み合わせ運用であると報告されています。
消費者の約6割がAIで商品検索、7割が生成AIで検討完了するのは、もうマーケティングの世界では常識になりつつあります。AIを使えない方々は取り残されて行ってしまうのです。AIと進化していく我々も、ディストピア的な社会ではなく、AIと共生していける、そんな未来を目指せるようにすると言う心構えが大変重要なんだなと思いました。
いかがでしたでしょうか?今週も多くのAIニュースがありましたが、面白いニュースはありましたか?あなたのお役に、少しでも立てられましたら、幸いです。


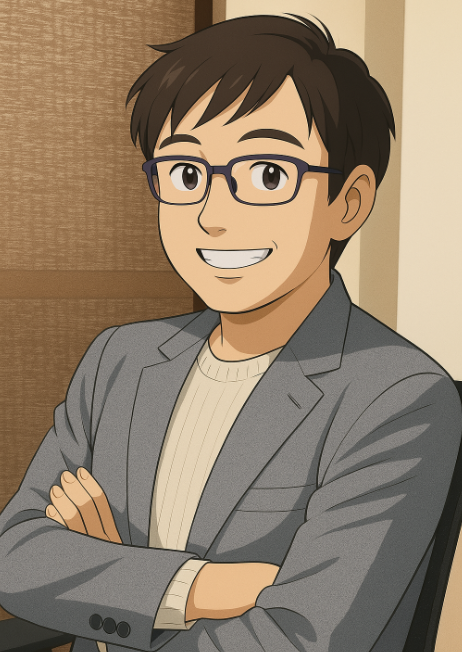


コメント